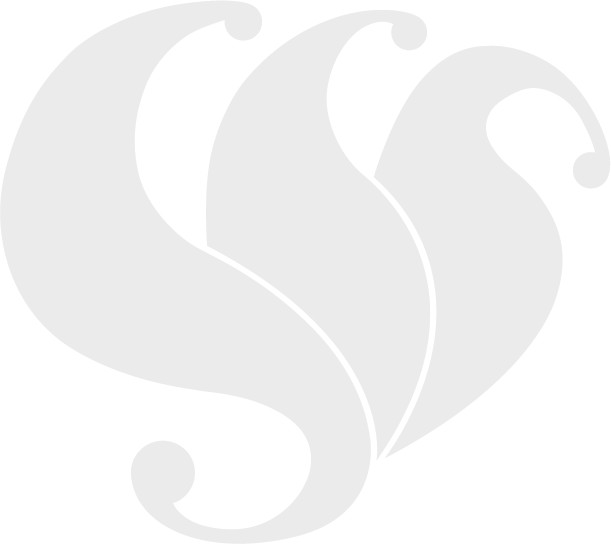お探しのページは見つかりません
NOT FOUND
申し訳ございませんが、お探しのページは移動または削除されたか、
URLが変更になったか、URLが正しく入力されていない可能性がございます。
なお、このページは5秒後にトップページへ自動的に移動します。
移動しない場合はお手数ですが、下記のボタンより再度アクセスしてください。
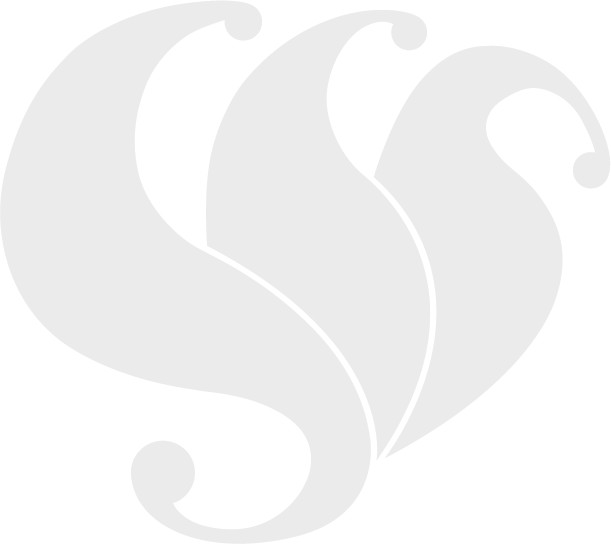

お探しのページは見つかりません
NOT FOUND
申し訳ございませんが、お探しのページは移動または削除されたか、
URLが変更になったか、URLが正しく入力されていない可能性がございます。
なお、このページは5秒後にトップページへ自動的に移動します。
移動しない場合はお手数ですが、下記のボタンより再度アクセスしてください。